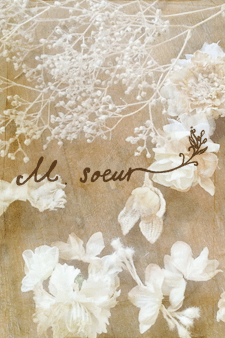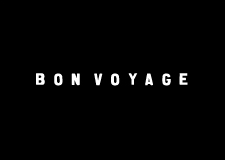Interview : July 9, 2015 @ 15:12
紐トーク Vol.02──中島ノブユキ『散りゆく花』を紐解く その2
オリジナルアルバム『散りゆく花』を、自身の音楽レーベル「SOTTO」からリリースした、音楽家”中島ノブユキ”。
”室内楽=アンサンブル”なサウンドを展開した今作を、いろいろな方面から紐解いているインタビューの後編。
最終回は、”中島ノブユキ”自体を紐解く(紐トーク)。
─今作もそうなのですが、
中島さんの楽曲は、たとえば、こうやって会話をしていたりしても、
そのヒトとヒトの間をココチよく埋めてくれる媒介みたいな感じなんですね。
会話をしていても気にならないんですけれど、気になる感じ。
ニュアンスを伝えるがスゴくむずかしいのですが。。。
ソレが毎回のコトなので「中島さん、やっぱり天才だなー!」とおもって、
アルバムを聴かせていただいているんです。
作曲において、そういう、、、ナニかコツのようなモノってあるんですかね(笑)?
コツかー。
ナンでしょうねー(笑)。
─「聴いているとビジュアルが浮かぶ」というお話は、以前から中島さんにしているかとおもうのですが、
この、いい意味での生活の音楽というか、BGMとして心地よい感じに仕上げてきている気がするんですよね。
会話をしてても集中しても聴ける。
この不思議な音楽をどうやってつくっているのかが、気になっていて(笑)。
たとえば、ベースとなっている、いわゆる影響を受けた音楽が、そういう感じなのでしょうか。
ドチラかといえば、けっこうドぎつい音楽が好きなんですよね。
あまりサラっとした感じのものは、、、自分自身あまり聴かないかなー。
─そうなんですか!?
すごくエッジの効いたものとか、ラウドなものとか、
現代音楽もそうだし、ファンクでもそうだし、ニューウェイヴでもナンでも。
曲づくり的にエゲツないつくりをしているものも好きだしね。
そういうものが好きだったから。
だから、、、ナンでなんでしょうねー(笑)。
─逆に自身でつくられる曲に関しては、
いわゆる反面教師的なものがあったりするんでしょうか?
ひとつ言えるとしたら、、、
楽器のつかい方として、すごく経済的なつかい方をするんですよ。
お金的な話ではなくて、、、その楽器がムリをぜず、最大限に充実してひびくようにって。
特殊な奏法とか、音色とかを聴かせようとかは特別な効果をねらうとき以外はつかわない。
それは曲づくりも一緒で、ムリヤリ楽曲の頂点をつくって、
そこに向けての下準備して曲を際立たせようとかというかんがえがないんです。
むしろ、なるべく自然に、もしかすると空気のように、その楽器の演奏者がその音楽の中に、
ふんわりと溶け込めるような感じをを目指して曲をつくったり、
編曲をつくったりというような傾向はあるかもしれないなー。
─要因として、それは大きいカモですね。
ムリせず聴けるというか。
たとえば、ヴィオラという楽器は、ボクはすごく好きなんです。
ヴァイオリンのような華やかさはないし、チェロのように支えていくようなものともちがう。
ドチラかというと影にかくれて、
真ん中をしっとりと埋めるような音域でもあり音色でもあり、という特性の楽器。
ボクは逆にヴィオラのそういうところを際立たせたいとおもうワケです。
つまり、ヴィオラを旋律楽器としてつかいたいと。
ヴィオラが聞こえるように、
ヴァイオリンとヴィオラの音域を逆転させたりするのね。
─なるほど。
それはオモシロいですねー。
すると、その楽器の全体的な役割分担から解きはなたれるので、
より充実したカタチで弾いてもらえるフレーズ感がでるのかもしれないね。
ときには「これは、むずかしいフレーズですね」と言われちゃったりもするんだけれど(笑)。
基本的にはムリせずに、なるべくある種のピークはつくらずにつくるようにしている、
そういう部分はありますね。
─中島さんの楽曲は、音に押されるんじゃなく、すっとカラダに入ってくる、、、
浸透するんですよね。
中島さん自身は、意識してつくっているワケではないんですよね?
そうそう。
いろいろな要素がカラみあって結果的にそうなっているんだとおもう。
もしかしたら、それは室内楽という音楽のある種の特性というか、
あるひとつの断面なのかも。
ボクは、ファーストアルバムのときから、
サウンドとして室内楽を追いもとめているんですよ。
そして、演奏者が好きなワケで、けっして”楽器”を愛しているワケではないのね。
たとえば、バンドネオンという楽器を愛しているワケではなく、
“北村聡”というヒトが弾くバンドネオンが好きなのね。
─なるほどー。
たとえば、ファーストアルバムの『エテパルマ』だったら、
“山中(光)”さんというヴァイオリニストがいて、
山中さんの弾くヴァイオリンの音色が好きで、
別にヴァイオリンの音色だけがほしいというコトではない。
おなじように、『エテパルマ』と『パッサカイユ』で弾いてくださった、
“矢島(富雄)”さんのチェロが好きで、矢島さんにぜったい弾いてほしいと。
それから、ヴィオラの”鈴木民雄”さん。
民雄さんの弾く音色がほしくて”民雄”さんに演奏をおねがいをする。
つまり──。
─楽器ではなく、ヒトで選んでいるんですね!
そう!
そのヒトが弾くその楽器だからその音がほしい!というコトなんですよ。
だからといって、ほかのヒトではその曲が演奏できないのか?
といったら、そうではないんですけれど。
レコーディングというのは言うなれば初演の記録でもあるワケで。。。
─それは、たとえばヴィオラの音がほしいからといって、
ただ弾けるヒトにたのんだ作品であれば、
もしかしたら違和感があるのかもですね。
ある意味、キチンと中島さんと溶けこんだ方とやられているので、
ダレもヘタな主張はせず、そういう感覚を生みだしている要因のひとつなのカモです。
アルバムをつくるときに、まずいちばんにやることはメンバーを決めるんですよ。
このヒトが弾いてくれるのならこのフレーズにしよう!とか、
こういう音域にしよう!とか。
─中島さんが、その演奏者の良い部分を知っているからそこをチョイスする、、、
ある種の編集力みたいなものかのカモですね(笑)。
コレが、編集力なのかはわからないけれど(笑)。
でも、コレってけっこう贅沢な考え方なのかなとおもいますよ。
たとえば、映画に例えれば、監督と脚本を一緒にやられている方が、
役者を想定して脚本を書いているワケですからね、かなり贅沢。
“小津安二郎”さんなんて、それができたとおもうしね。
ソレが、今作でも実現できているというのはありがたいとおもいますよ。
─うむ、、、中島さんの音づくりのコアな部分のひとつが紐とけたような気がします。
極端にいうとヒトが重要。
それくらい、そのヒトが弾く楽器というのは自分のなかでは重要な位置なのかなー。
─ちなみに、中島さんのアルバムでは、
中島さん自身のピアノを主張するつくりにしていないですよね。
もちろんピアノソロ作品は別ですが。。。
とくに今回はそうかもしれないねー。
でもね、制作途中にいろいろ紆余曲折があって。。。
ミックスは、『メランコリア』以来ずっとエンジニアの”奥田泰次”さんにおねがいしているんだけど、
コレだけ一緒に作品をつくっている”奥田”さんでも、
最初はピアニストのアルバムだからということで、ピアノの音が、、、
─大きかったんですか?
そう!デカかったのよ、、、最初におくられてきたものが。
もちろん、それはそれである種のカタチになっていて、
すばらしいとおもったんですけれどね。
なんだけれど、
今回は、ピアニストが真ん中にいてまわりをしたがえているような作品ではなく、室内楽。
すべての演奏者がそれぞれの役割のなかで、おなじ地平にいる作品なので、
ナニかが中心にあってまわりがそれを取りかこんでいるというサウンドにはしないでほしいというコトで、
ピアノの音量をずいぶん下げてもらったという経緯があるのね。
─そうだったんですね。
それはすごく感じるんですよ。
中島さんの作品に関しては、主張がないワケではないのですが、それを感じさせない。
作品としてバランスがとれているのかなと。
それは、音づくり、録音のときからはじまっていて、
ミックスダウン行程のなかでも話し合いをして、
最終的なところに落ちつくというのはありますね。
─それも要因のひとつでしょうね。

そういえば、『先行試聴会』をやられてましたが、
けっこういろいろなトコロをまわられてましたね。
手ごたえ的にはどうでしたか?
すごく、オモシロかったですよ。
もっといろいろなところに行きたかったなーとおもって。
─基本は試聴だから、
普段、演奏しなければ行かないような場所にも行かれたとおもいますが、
ココはオモシロかったなー、、、みたいな場所はありますか?
ドコもそれぞれ、ソコならではという場所でやらせていただいたので思い出深いのですが、
今回でいえば、はじめていったところで、富山の氷見、、、港ですよね。
会場は、港をはなれて山にヒョロっとはいったところにある、
「SAYS FARM」というワイナリーだったんだけれど、
たまたまワイナリーに来たヒトにも参加してもらったりして、
今回の試聴会というか、「音をとどける」というコトにおいては、
すごく新鮮な体験でしたよ。
─まず、「試聴会」というモノをやるというのがオモシロいとおもいましたよ。
ほかのヒトはおそらくやらないじゃないんですか?
最近は(笑)。
やらないよねー(笑)。
でも、ボクの中ではそんなに違和感はなかったのね。
むかしさー、ジャズ喫茶とか、ああいうトコロで、
レコードの新譜が出るとやってたじゃない?
─たしかにやってましたねー!
ソコの店主とかが買った新譜のレコードを、
常連のヒトに聞かせる、いわゆる「レコードコンサート」。
ソレがイメージにあったのかもしれない。
だから、そんなに違和感があったつもりはなかったんだけれど。。。
─いまの30代以下くらいの世代は、「試聴会!?ナニ?」ってなるのかなーと。
そうそう!
今回、各所で実際的な宣伝を、
各会場とか、そこに携わってくれているヒトにおねがいをしたんだけれど、
みなさん「こまった!」って言ってたよね。
つまり、今回、おこなわれるコトを、
どういう風にお客さんに説明していいのかわからないって(笑)。
─「ナニをするの?」って、なっちゃうかもですね(笑)。
ピアノがあるところでは、10分とか15分くらい演奏したんだけど
ピアノがない会場は「演奏はありません」って銘打っているから、
すると、これをどうやって説明すればいいかが「むずかしい!」って(笑)。
─たしかに、むかしはありましたね、「レコードコンサート」。
しばらく、そのコトバを聞いてなかったです。
ソレをやりたかったのね。
─「試聴会」で全国をまわるって、しかも本人がいくって、
もしかしたらそんなヒトは中島さんが『40年ぶりの快挙!』とか、
そんなレベルなんじゃないですか(笑)!?
そんなに突飛なことをやったつもりはまったくないんだけどね(笑)。
─たとえば、トークショウなんかもやったりするじゃないですか?
そうそう!
トークを交えるというのが、重要なのかなーと。
せっかく自分自身もいるし。
今回は、映画監督の”甲斐田祐輔”くんが撮ってくれた、
録音風景のフィルム上映をしたりとかしてさ。
でも、プロジェクターは自分で持っていったのよ(笑)。
小型のモノをかついでさ。
─意外と、プロジェクターとかって、あるところってすくなかったりしますからねー(笑)。
けっこう大変だったんだけれど、オモシロかったですよ。
─ちなみに、音的な環境はどのようにされたんですか?
その、、氷見のワイナリーとかはあったんですか?
あのねー、なかった(笑)。
なかったから、京都でお世話になった「下村音響」の”下村”さんという方がいて、
『飛飛機械(ピュンピュンマシーン)』っていう、
ダブのヒトがつかうようなエフェクターを制作している方なんですけれど、
その方がワイナリーまでスピーカーを持ってきてくれたんですよ。
“下村”さんには車で移動する際にもお世話になって、、、
だから、かなり手づくり感が満載(笑)。
─いいですねー。
いーんですよ!
ホントに有り難いです。
自分ひとりではできないコトだったんですけれど、
そういう方にお手伝いいただいてできたって感じですね。
それに、「コレ、おもしろいねー!」ってなって、
「ほかの企画でもやりましょう!」と言ってくれた方もいて、
やってよかったとおもいました。
─ピアノのないところでもできますからね。
それも大きいかな。
─さて、もうリリースツアーがはじまってますが、
今回は、編成だったりとか、、、どんな感じでかんがえているんですか?
今回はアンサンブル、室内楽の作品ということで、
再現するということを目的とするコンサートももちろんあります。
たとえば、2015年10月18日の東京会場は、
完全にレコーディングしたときのメンバーと編成も一緒で9人編成でのコンサート。
ほかの会場は、ギターの”一馬”くんとふたりだったり、”北村”くんとふたりだったり、
ベーシストの”田中伸司”さんを加えて4人でや演奏するコンサートとか。
録音の時とは違った編成でやると、楽曲がまたうごきだすのね。
─ちがうモノになりますよね。
そう。
それがまた自分自身でもおどろきで、やっていて新鮮なんですよ。
4月30日に「フクモリ」の万世橋店で演奏したときには5人編成だったので、
おなじ曲をやってもちがうヒビキをまとうし、
ちがう躍動感というか、リズム感が生まれるから、
ちがったカタチで提示できたのはおもしろかったかな。
それが今回、長いスパンでツアーを組んだ理由のひとつでもありますね。
─東京は求道会館でですが、またオモシロい場所でやられますね。
ここはヒビキがうつくしいトコロで、
ピアノもまたすばらしいモノが置いてあるんですよ。
─それで選ばれた感じなんですね。
場所によって、演奏がちがったり、音がちがったりというのをたのしんでほしいですね。
そうなんですよ。
すごくしずかな曲がワイルドな曲になったりするし、
ダイナミックな曲をより繊細にニュアンスをつけて演奏するとか、
やっぱり会場の空気感に影響されて演奏のスタイルも会場ごとに変わるので、
すごく楽しみなんですよ。
ぜひ聴きにきていただきたいですねー。
─今回のお話は、中島さんのコトがいろいろ紐解けたような気がしますよ。
ありがとうございました!
コチラこそ、ありがとうございましたー!
(おわり)
□アルバム情報
中島ノブユキ
『散りゆく花』
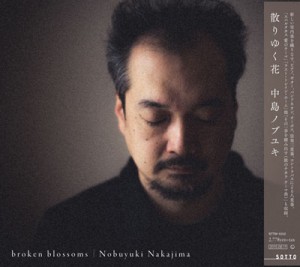
価格:¥2,778(税抜)
レーベル:SOTTO(STTM-1002)
>>>レビューはコチラ
「SOTTO」オフィシャルサイト:http://www.sotto.maison/
“中島ノブユキ”オフィシャルサイト:http://www.nobuyukinakajima.com/
>>>『散りゆく花』リリースツアー日程などの詳細はコチラ
>>>紐トーク Vol.02──中島ノブユキ『散りゆく花』を紐解く その1
This entry was posted on Thursday, July 9th, 2015 at 15:12 and is filed under Interview. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.